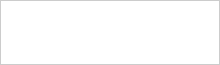樟脳は樟樹(クスノキ)より、採りますが、その樟樹(クスノキ)は、常緑広葉樹です。
しかし、実は常緑樹といっても秋には落葉して、翌年の春までに、葉が全部入代るのです。ですから、冬になると葉の量が減って見えます。(但し、冬に葉の全部が無くなってしまうわけではありません。)
樟脳の化学式は「C10H16O」で、植物精油から得られた「結晶性テルペノイド化合物」です。名前上の「脳」は、camphorの訳で、「カンフル剤」としても知られています。かっては、強心剤としても使われていたのです。また、血行促進、鎮痛、消炎剤としても使われていました。「脳」を使用されたものでは「薄荷(ハッカ)脳」(メントール)(mint camphor)や「龍脳(ボルネオール)」(borneo camphor)なども知られています。
葉の裏側の葉脈の根本から1番目か2番目、たまに3番目の枝分かれの部分に小さな「黒い瘤(コブ)」があります。全部の葉に付いているので「こうした葉」と思い込んでいると、違うのです。瘤の中央に穴が開いていて、「白いダニ」が共生しているのです。
このダニが樟樹を守っているのです。効力とも関係があるのかも知れません。
硝酸セルロースと樟脳と合成すると「セルロイド」が得られます。プラスチックが出現するまで、セルロイドが眼鏡のフレームや、洋服の襟や、おもちゃ、飾りなどに多用されて来ました。しかし、燃えやすい欠点があり、アセテート、ポリエチレン、プラスチックなどへ取って代えられて来たのです。
命を縮める「殺虫・防虫剤」
神経毒は、神経の繫がりに障害を与える毒です。これが体内に蓄積すると遺伝子障害や癌などの発生に影響を与える可能性が高くなります。現代の先進国での出生率の低下と関係が疑われている要因の一つになっています。また、老人性痴呆症、アルツハイマーの要因の一つとしても疑われています。
現在「殺虫・防虫剤」で販売されている製品は、「ナフタリン系」「パラジクロロベンゼン系」「ピロスロイド系」と「樟脳」に分けられます。しかし、「ナフタリン系」「パラジクロロベンゼン系」「ピレスロイド系」ともに体内の蓄積による人体への影響が懸念されています。とりわけ、「無臭」になっているものが主流になりつつあり、様々な警告が為されています。そのような中で、古くより伝えられて来た「樟脳」が再評価されて来ているのです。やはり、安全度は高いのです。